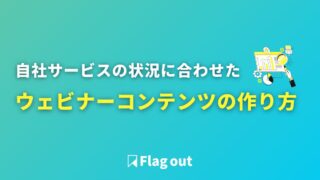「展示会やオフラインイベントでの集客が難しくなってきた」「コストを抑えつつ効率的にリードを獲得したい」といった課題を抱えているのであれば、オンラインカンファレンスをおすすめします。
オンラインカンファレンスとは、インターネット上で行う大規模な会議やイベントを指します。過去に当社で開催したオンラインカンファレンスのイベントページをご覧いただくとイメージがしやすいかもしれません。
過去当社で開催したオンラインカンファレンス
本記事では、オンラインカンファレンスのメリット・デメリット、開催までの流れ、そして成功させるためのポイントをご紹介しています。
マーケティング施策としてオンラインカンファレンスを検討しているご担当者様は、是非最後までご覧ください。
オンラインカンファレンスが注目される背景
展示会やセミナーは、会場費や機材費、スタッフの交通費など運営コストが高く、継続的に実施するには大きな負担がかかっていました。参加者側としても、移動や宿泊の手間がハードルとなり、遠方在住者や多忙なビジネス層にとって参加しづらい状況がありました。
加えて、新型コロナウイルス感染症の影響でリモートワークが急速に普及すると、オンラインで情報を得る行動がさらに加速しました。YouTubeやTikTokは以前から利用されていましたが、「効率よく短時間で学びたい」という需要が一層高まり、長時間拘束される会場型イベントは敬遠されやすくなったのです。
こうした時代の変化に対応する手段としてオンラインカンファレンスが広がり、BtoBビジネス分野ではリード(見込み顧客)獲得や企業ブランディングに活用されるようになっています。
オンラインカンファレンスのメリット
オンラインカンファレンスには、オフラインカンファレンスにはない利点があります。マーケティング施策として成果につなげるために、まずは特徴を理解しておきましょう。
地理的制約を超えたリーチ
オンラインカンファレンスは移動や宿泊の必要がないため、これまでオフライン型イベントでは集客が難しかった地方在住者や海外の見込み顧客にも参加してもらいやすくなります。例えば、都市部で開催していた製品紹介イベントをオンライン化すれば、北海道や沖縄など遠隔地にも同時にアプローチできるでしょう。
地理的な制約を受けずに参加者を集められることで潜在顧客との接点を広げやすくなり、商談や購買につながる機会も増やせます。
コストを抑えられる
オフラインでイベントを開催する場合は、会場のレンタル料やブース設営費、スタッフの交通費や宿泊費、機材の運搬費など多くのコストが発生します。
オンラインカンファレンスは大規模な会場を借りる必要がなく、自社の会議室や配信スタジオなど既存設備から実施できるため、支出を大幅に抑えることができます。
また、録画配信やアーカイブを活用することで、一度作成したコンテンツを継続的に使用でき、長期的な費用対効果も高められるのです。
参加者データを収集できる
オンラインカンファレンスでは、参加登録時に入力された属性情報だけでなく、視聴開始や終了時刻など詳細な行動データも取得できます。
例えば、終了後アンケートを実施すれば、興味関心が高い層を有望なリードとして営業部門に引き継ぐことができ、商談化の確率を高めやすいでしょう。
開催形式を選べる
オンラインカンファレンスの開催形式は次の3つに分けられます。
| 形式 | 特徴 |
|---|---|
| ライブ配信 | リアルタイムで実施する形式。チャットや質疑応答など双方向性があり、臨場感を演出できる |
| 録画配信 | 事前に収録した映像を配信する形式。参加者が都合の良い時間に視聴でき、繰り返し再生も可能 |
| ハイブリッドイベント | ライブと録画を組み合わせる形式。リアルタイム性と視聴しやすさを両立できる |
目的や参加者の状況に合わせて形式を選べるため、「製品発表会はライブで行う」「専門性の高い内容は録画でじっくり視聴できるようにする」といった組み合わせも可能です。
登壇者の予定に合わせやすい
外部に登壇を依頼したくても、これまでは長距離移動や前日入りなど負担が大きく、日程を確保してもらうのが難しい状況でした。しかしオンラインカンファレンスなら会場まで移動する必要がないため、海外在住や多忙な専門家からも登壇の承諾を得やすくなります。
また、録画配信を活用すれば事前に収録した映像を当日に流せるため、登壇者がイベント当日に予定を空ける必要もありません。登壇者の候補が広がることで質の高いコンテンツを提供しやすくなり、参加者の満足度向上にもつながるでしょう。
オンラインカンファレンスのデメリット
オンラインカンファレンスには多くのメリットがある反面、注意すべき要素もあります。ここでは、特に発生しやすいデメリットをご紹介します。
離脱率が高くなりやすい
オンライン開催では、主催者側にとっては、自宅やカフェなど自由な場所から視聴できるため、多くの参加者を集めやすいのが特徴です。しかし参加者側にとっては、会場で講演を聞く場合と異なり、メール対応や作業をしながら視聴する「ながら見」が起きてしまう懸念もあります。
内容への興味が薄いとすぐ離脱されてしまうことも多く、オフライン開催に比べて平均視聴時間が短くなるケースも少なくありません。
通信トラブルのリスク
オンラインカンファレンスは配信環境に依存するため、音声の途切れや映像遅延といった技術的な問題が発生するリスクがあります。たとえ内容が優れていても、わずかな不具合が視聴体験の質を下げ、イベント自体の満足度の低下やカンファレンス途中での離脱につながりかねません。
対面に比べて訴求力が弱まる
オンラインでは画面越しのコミュニケーションになるため、登壇者の表情や声の抑揚といった要素が十分に伝わりません。会場特有の熱気や一体感も得にくく、参加者との心理的距離を縮めることが難しくなります。
その結果、対面で実施する場合と比べて参加者の感情を動かす力が弱まり、印象に残りにくい傾向があります。
オンラインカンファレンスの開催方法
オンラインカンファレンスを成功させるには、ここまでのメリットとデメリット理解しつつ、計画的に進めることが欠かせません。ここでは、企画から開催後のフォローまでの大まかな流れをご紹介します。
- 企画・設計:テーマやターゲットを明確にし、登壇者のアサインやプログラム構成を行います。
- プラットフォーム選定:Zoom・EventHub・Vimeoなど、目的や規模に合った配信ツールを選びます。
- 集客・告知:SNS広告、専門媒体への掲載、メール配信、SEO、パートナー企業との連携などで告知します。
- 当日の運営:リハーサルを実施し、進行台本を準備して役割を明確にします。配信トラブルに備え、機材やネットワーク環境も事前に入念にチェックします。
- フォローアップ:アンケートを回収し、参加者データを営業チームに共有します。
オンラインカンファレンスを成功させるポイント
KGIとKPIを設定する
まずは最終的な成果指標(KGI)を定め、その達成度を測る中間指標(KPI)を明確にします。例えばKGIを「商談件数の創出」とするなら、KPIには「参加申し込み数」「視聴完了率」「アンケート回答率」などを設定するとよいでしょう。
目標を先に決めておくことで、どの指標をどのタイミングで達成すべきかが明確になり、全体設計に一貫性が生まれます。
コンテンツ価値を高める
参加者にとって魅力的な内容でなければ、途中離脱が増え、リード獲得や商談にも結びつきにくくなります。参加者が抱える課題や関心を丁寧にリサーチし、解決に直結するテーマを設定することが大切です。
さらに登壇者には専門性や発信力の高い人物を選び、話し方や資料は理解しやすさを重視します。情報量の多さだけでなく、「理解しやすいか」「実務に役立つか」といった観点で内容を磨き上げることで、コンテンツの価値を高められるでしょう。
参加者の体験を設計する
オンラインでは視聴者側が集中力を維持しにくいため、飽きずに最後まで視聴できる仕組みを用意することが欠かせません。単調な資料ではなく、視覚的に訴えるスライドや動画を取り入れて構成にメリハリをつけます。
さらに「講演と講演の間に自社CMを挟む」「チャットや投票機能で双方向性を持たせる」など、受け身にならない工夫を盛り込みましょう。
リハーサルを行う
どれほど内容が優れていても、配信トラブルが起きれば満足度は大きく損なわれます。本番と同じ環境でリハーサルを実施し、映像・音声・ネットワーク環境を入念に確認しておきましょう。
また、プラットフォームの操作方法やトラブル発生時の対応手順を関係者に共有しておくことで、当日の混乱を防げます。
データをもとに改善する
オンラインカンファレンスは対面型よりもデータを集めやすいという特徴があります。申し込みページでの属性情報だけでなく、入退室時間やアンケート結果なども幅広く回収して活用しましょう。
例えば視聴完了率や離脱率の傾向を分析すれば、どのコンテンツに関心が集まりどこで離脱が起きているかを把握でき、次回以降の改善に結びつけられます。
まとめ
オンラインカンファレンスは地理的な制約を超えて見込み顧客にアプローチでき、コストを抑えながら効率的に集客・商談化を進められるとして注目を集めています。
一方で、離脱率の高さや通信トラブルなどオンライン特有の課題もあるため、事前準備や体験設計、データ分析を通じて改善を重ねることが成功の鍵となります。
ただし、オンラインカンファレンスには幅広い知識が求められるため、「自社だけで運営するのは難しい」と感じる担当者も少なくありません。その際は、フラグアウトが提供するウェビナー支援サービスの活用をご検討してみてください。企画から当日の運営まで一貫してサポートしております。