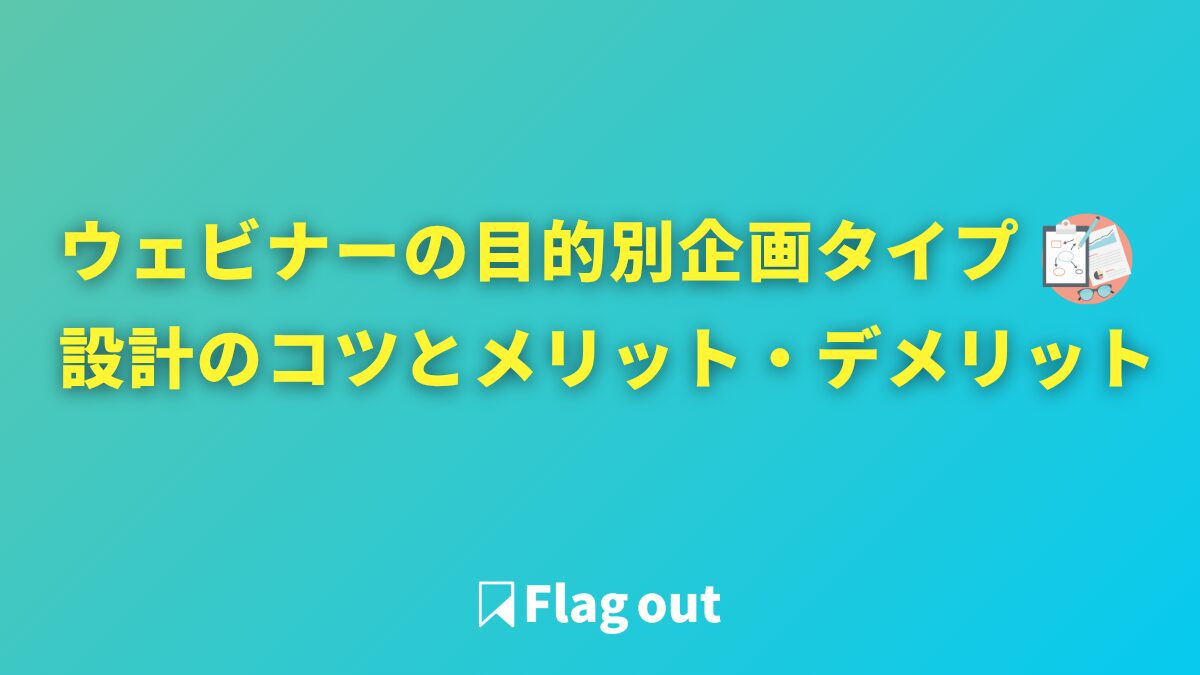ウェビナーを実施しても「思うように集客できない」「商談につながらない」といった悩みを抱えるウェビナー担当者は少なくありません。
ウェビナーの成果を左右する最大のポイントは、誰に・何を届けるかという企画段階にあります。
本記事では、ウェビナーを目的別に3つのタイプに分け、それぞれの効果的な進め方をご紹介します。自社のターゲットやフェーズに合ったウェビナーを設計するために、是非ご活用ください。
■はじめに|なぜウェビナーの「目的設計」が成果を左右するのか?
マーケティングにおいてウェビナーは一般的な施策となりましたが、期待通りの結果が得られないケースも多く見られます。その原因のひとつが、目的が曖昧なまま企画を進めてしまっていることです。
ウェビナーは、届けたい相手や達成したいゴールによって、内容や構成を大きく変える必要があります。
例えば、まだ自社を知らない層に対していきなりサービス紹介をしても響かず、かえって敬遠されてしまうでしょう。一方で、導入を検討している層には、成功事例や具体的な効果を示すことで、商談への一歩を踏み出してもらいやすくなります。
そこで当社では、ウェビナーを目的別に以下の3タイプに分類しています。
- 潜在層向け:認知獲得型ウェビナー
- 情報収集層(準顕在層)向け:関係構築型ウェビナー
- 比較・検討層(顕在層)向け:商談直結型ウェビナー
次章からは、それぞれのタイプに合った構成のポイントを詳しく解説していきます。ウェビナー後の反応を改善するためにも、まずは「目的設計」の視点から見直してみましょう。
■潜在層向け:①認知獲得型ウェビナー(例:カンファレンス型)
認知獲得型ウェビナーは、まだ接点のない潜在層に「自分ごと化」のきっかけを与える施策です。業界トレンドや社会的テーマを切り口に、自社の課題に気づき、行動の必要性を感じてもらうことが目的です。
認知獲得型ウェビナーの目的
潜在層に対しては、サービス紹介やセールス色の強い内容を伝えても、関心を持たれにくく逆効果になることもあります。
そこで効果的なのが、業界トレンドをテーマにしたカンファレンス型のウェビナーです。外部登壇者によるパネルディスカッションなどを通じて、「気づき」や「共感」を自然に引き出す構成が有効です。
ただし、テーマが抽象的すぎると「何を伝えたかったのか」がぼやけてしまいます。潜在層の興味を引きやすい話題、かつ自社の価値をさりげなくアピールできる内容を企画します。
認知獲得型ウェビナーのメリット
外部ゲストや著名人を招くことで、イベント自体の話題性が高まり、100〜500名以上の大規模な集客につながるケースもあります。
さらに、業界や社会全体の課題をテーマに設定することで営業色を抑えた設計が可能となり、自社と初めて接点を持つ参加者にも興味を持ってもらいやすいのが特徴です。
認知されていない層に安心感を与えながら、自社の思想やスタンスを自然に伝える絶好の機会になります。自社名の認知向上や信頼構築の起点として非常に有効なアプローチといえるでしょう。
認知獲得型ウェビナーのデメリット
認知獲得型ウェビナーは大規模な集客が見込める一方で、参加者との関係性が浅いため、商談にはつながりにくいのが現状です。「興味を持っただけで終わる」「内容が抽象的で印象に残らない」といったケースも少なくありません。
そのため、あらかじめナーチャリング施策を組み込んでおきましょう。具体的には、フォローメールの送信やホワイトペーパーの提供、ニュースレターなどが有効です。
また、カンファレンス形式は、登壇者との調整や集客ページの作成、配信体制の準備など工数がかかりやすい点にも注意が必要です。伝え方にこだわるほど準備も複雑になるため、リソースとのバランスを見ながら無理のない形で進めていきましょう。
■情報収集層(準顕在層)向け:関係構築型ウェビナー(例:共催セミナー型)
情報収集層(準顕在層)にアプローチするなら、信頼関係を築くことに主眼を置いた「関係構築型ウェビナー」が有効です。自社の事例やユーザー視点の情報を盛り込むことで参加者の理解や納得感が深まり、次の意思決定につなげやすくなります。
関係構築型ウェビナーの目的
情報収集層(準顕在層)段階にいる顧客は、すでに課題意識を持っているものの、「本当にこのサービスで良いのか」と判断に迷っている段階です。この層に対しては、信頼を深めるための情報提供や共感を促す構成が重要になります。
具体的には、導入事例の紹介や実際のユーザーによる登壇を通じて、「他社でも成果が出ている」「自分たちと同じ課題を乗り越えている」と感じてもらうことが狙いです。
関係構築型ウェビナーのメリット
関係構築型ウェビナーは顧客視点での情報提供がしやすく、商談の前段階として有効です。特におすすめなのが、複数の企業が共同で開催する共催形式です。
一度に複数社のノウハウや事例を届けられるため、説得力が高まり、参加者の比較検討を後押しできます。
トークセッション形式や質疑応答など双方向の要素を取り入れることで、参加者との距離も縮まりやすくなります。
さらに、共催パートナーの顧客リストやネットワークを活用できるため、自社だけではアプローチが難しい層にリーチできる点も大きなメリットです。
関係構築型ウェビナーのデメリット
共催形式は効果的な一方で、調整の負荷が大きくなる点には注意が必要です。まず、自社とターゲット層が重なりつつ、商材が競合しない企業を見つけるのは簡単ではありません。同じターゲットを持ちながら、提供価値が異なる企業を選定する視点が欠かせません。
登壇内容のすり合わせやメッセージの方向性を一致させるには、事前の打ち合わせが不可欠です。テーマや規模にもよりますが、企画から開催までに1ヶ月半〜2ヶ月程度の準備期間を想定しておくと安心です。
また、役割分担が曖昧なまま進めてしまうと「誰が何を伝えるのか」が不明確になり、全体の訴求力が弱まる可能性もあります。進行や構成の主導権をどちらが握るのかも含め、合意形成を図るようにしましょう。
以下の記事では共催ウェビナーの特徴や流れをまとめていますので、ご参考ください。
■比較・検討層(顕在層)向け:商談直結型ウェビナー(例:課題解決型、サービス紹介、デモ訴求)
自社の商品やサービスに強い関心を持っている顕在層には、デモや導入後の効果を伝えて購買意欲をさらに高めることが重要です。以下に、ウェビナー後の商談に結び付けるためのポイントをまとめました。
商談直結型ウェビナーの目的
すでに接点を持っているリードへのアプローチのため、社内のリードリストに対して集客を行います。導入効果や納品までのフロー、料金の提示などより詳しい情報を提供し、意思決定を後押しします。
特に重要なのが、CTA(資料請求・個別相談・無料トライアルなど)の設計です。視聴直後のタイミングで行動につなげられるよう、画面上の表示やセミナー後のフォロー施策も含めた導線をあらかじめ計画しておきましょう。
商談直結型ウェビナーのメリット
商談直結型ウェビナーは、導入意欲の高い「今すぐ客(ホットリード)」に向けて、具体的な製品訴求ができる点が大きな特長です。
例えば「製品名 × 活用方法」や「導入後のROI(投資対効果)」にフォーカスした内容で実施すれば、導入を本格的に検討している層に対して背中を押す材料を提示できます。
また、構成がシンプルで、他のタイプに比べて準備工数が少ない点も利点です。短期間で開催できるため、担当者の負荷を抑えつつ、商談創出の施策として組み込みやすいと言えるでしょう。
商談直結型ウェビナーのデメリット
商談直結型ウェビナーは自社の製品やサービスに特化した内容になるため、セールス色が強くなりやすい点が課題です。そのため、まだ検討段階に入っていない潜在層には訴求しにくく、参加者数が限定される傾向があります。
KPI(指標)を設定する際は申込数や参加者数ではなく、見積もり件数や個別相談の発生件数、成約率といった、商談フェーズに即した指標を軸に据えるようにしましょう。
なお、ウェビナー施策を始めたばかりでは判断材料が十分にそろっておらず、目標設定が難しいかもしれません。初期段階で高すぎるKPIを設定してしまうと、チームのモチベーション低下や施策の継続断念につながってしまいます。まずは仮の数値を設定し、実施後のデータを踏まえて段階的に見直していく方法が有効です。
■まとめ|目的に応じて企画を設計すれば、ウェビナーは確実に強化できる
ウェビナー施策で成果を上げるためには、「誰に向けたウェビナーなのか」を明確にした上で、内容・形式・訴求ポイントを最適化することが欠かせません。本記事でご紹介した3つのタイプをあらためて整理すると、以下のようになります。
| タイプ | 主な目的 | 有効な形式・テーマ例 |
| 認知獲得型 | 潜在層との接点づくり | カンファレンス・業界課題・トレンド |
| 関係構築型 | 信頼醸成・比較材料の提示 | 共催セミナー・事例共有・ユーザー視点 |
| 商談直結型 | 導入意欲の後押し | サービス紹介・デモ・成果訴求 |
自社が今アプローチしたい層はどの段階にいるのか?そのフェーズに応じたウェビナーを設計できているか?この視点で現状の施策を見直すことで、成果を最大化しやすくなります。
とはいえ、企画から運営、コンテンツ制作に至るまで、すべてを自社内で対応するのは容易ではありません。内製が難しい場合は、フラグアウトのウェビナーBPOサービスの活用も視野に入れてみてください。設計から実行までをトータルで支援し、目的に合ったウェビナーを共につくり上げます。