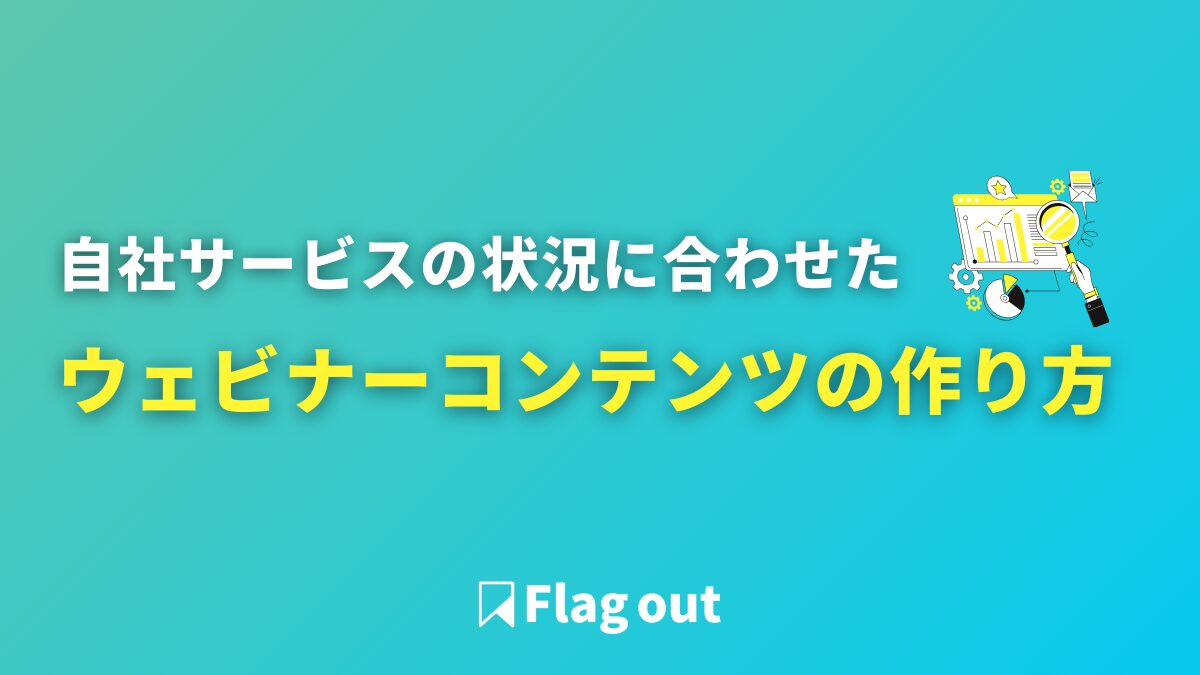「ウェビナーを開催しても、参加者が集まらない」「実施回数を重ねても商談や受注に結びつかない」そんな悩みを抱える担当者は少なくありません。
成果が出ない主な原因は、企画段階での設計にあります。誰に、何を、どのように伝えるか。そこが噛み合っていなければ、どれだけ実施しても成果にはつながりません。
本記事では、市場状況を4タイプに分類し、それぞれのポイントを解説しています。ウェビナーの効果を最大限に高めるために、ぜひ最後までお読みください。
■【まず知るべき】自社サービスの“市場状況”とは?
ウェビナーを成果につなげるには、まず自社のサービスがどのような市場状況にあるのかを見極めることが出発点となります。その際に有効なのが、「導入実績数」と「認知度」の2軸で自社の立ち位置を分類するという考え方です。
例えば、導入が進んでいない場合は、「なぜ導入すべきなのか」「他社と何が違うのか」といった検討材料を明確に伝える必要があります。一方で、導入実績はあるのに市場に知られていない場合は、そもそも課題の存在やサービスの意義を伝え、必要性に気づいてもらうところから始めなければなりません。
ここを正しく判断できなければ、どれほど手間をかけても、ターゲットに響くウェビナーにはなりません。
本記事では、自社の市場状況を4つのタイプに分けて整理しました。それぞれの状況に応じたウェビナー設計のポイントをご紹介しますので、自社に照らし合わせながらお役立てください。
■【4タイプ別】市場状況に合わせたウェビナーコンテンツ設計法
市場状況は、「導入実績数」と「認知度」の2軸によって4種類に分類できます。
- 導入企業が少ない × 認知度が低い(新市場・新サービス)
- 導入企業が少ない × 認知度がある(黎明市場・競合比較が始まる)
- 導入企業が少ない × 認知度が高い(カテゴリ認知後の差別化フェーズ)
- 導入企業が多い × 認知度が高い(成熟市場)
以下では、それぞれのタイプにおいて、どのようなウェビナーを企画すべきかを解説します。
A Type|導入企業が少ない × 認知度が低い(新市場・新サービス)
サービスカテゴリまたは自社サービスの認知度も導入実績もほとんどない段階では、参加者の多くがサービスカテゴリそのものに関心を持っていない、もしくは存在すら知らない可能性があります。この段階でプロダクトの説明や価格の話をしても、聞き手には届きません。
まずは業界の課題や背景を丁寧に伝え、「なぜ今、このテーマに向き合う必要があるのか」を納得してもらうことが重要です。講座型の構成で課題に気づかせる内容や、先進的に取り組む企業の実例を紹介する対談形式が効果的です。視聴者に「これは自分たちの課題だ」と感じてもらえれば、次のアクションにもつながりやすくなります。
B Type|導入企業が少ない × 認知度がある(黎明市場・競合比較が始まる)
サービスカテゴリまたは自社サービスがある程度市場に認知され始めたものの、導入はまだ広がっていない段階では、見込み顧客の多くが比較・検討フェーズにいます。こうした層には、自社サービスを候補に入れてもらうことが目標です。ただし、機能や事例紹介を並べるだけでは、十分に伝わらない可能性があります。
おすすめは、課題解決へのアプローチを提示するセミナー形式です。例えば「属人化をなくすための3ステップ実践法」といった切り口を用いることで、具体性を持たせながら自社の強みを印象づけることができます。
また、競合との違いを明確に伝える比較型のコンテンツも有効です。「従来の紙運用にはどのような課題があるか」「他社サービスと自社サービスは何が異なるか」といったテーマを取り上げると、検討の土台に乗せやすくなります。
C Type|導入企業が少ない × 認知度が高い(カテゴリ認知後の差別化フェーズ)
サービスカテゴリや自社サービス自体は広く知られているものの、導入があまり進んでいない段階では、「類似サービスと何が違うのか?」という視点で見込み顧客に訴求する必要があります。
B Typeと似ているように思えるかもしれませんが、C Typeではサービス内容に対する一定の理解があるため、より深い情報が求められる点が異なります。
このタイプに有効なのは、特定機能の実用性や成果にフォーカスしたウェビナーです。「この機能によって日報作成が30分短縮できた」といったように、実際の活用イメージを交えて説明することで、参加者に導入後の姿を明確に思い描いてもらえます。
また、操作画面を見せながら進行するデモ形式のセッションも有効です。使いやすさや導入後の定着を視覚的に伝えることで「自社でも実現できそうだ」と感じてもらいやすくなります。
ただし、スペックや機能を一覧化しただけの資料では印象に残りにくいため、現場での使われ方や効果の出方をストーリーとして伝えることを意識しましょう。
D Type|導入企業が多い × 認知度が高い(成熟市場)
市場に広く浸透し、導入企業も増えてきた段階では、「実績◯社」という訴求で十分なように感じるかもしれません。しかし、意思決定を後押しするには、「本当に成果が出るのか」「現場で使いこなせるのか」といった実務面の不安を払拭する必要があります。
例えば「3ヶ月で社内定着を実現した企業が取り組んだ工夫」を紹介すれば、視聴者は自社に置き換えて考えやすくなります。また、「成果を出している企業に共通する運用ルール」や「定着率の高いチームが実践している活用法」といったテーマも効果的です。
使いこなすまでのプロセスを丁寧に伝えることで、導入の決定打となるでしょう。
■【全タイプ共通】成果に繋げるためのウェビナー運営のコツ
ウェビナーの内容を市場タイプに応じて設計しても、視聴者に正しく伝わらなければ成果には結びつきません。どのタイプにも共通して重要なのは、「何をどう見せ、どう届けるか」という視点です。
ここでは、ウェビナーを企画する際に意識したいポイントをご紹介します。
成功事例・インタビューは“ストーリー”で語る
成果や数値を並べるだけでは、参加者の印象には残りにくいものです。
どのような課題に直面し、なぜ導入を決めたのか。現場ではどのように活用され、どんな変化が起きたのか。こうした背景をストーリーとして描くことで、聞き手は自社の状況に重ねながら内容を理解できます。
例えば「当初は社内の理解が得られず苦労した」といったエピソードが加わるだけで、臨場感が生まれます。感情や状況の変化を含んだ語りには共感が生まれやすく、検討材料としても強い印象を残せるでしょう。
数値データは“同業界・同規模”で示すと効果的
数値データを示す際に重要なのは、自分ごと化できるかどうかです。どれだけ優れた成果でも、業種や規模が異なる事例では現実味が薄れ、説得力も下がります。
例えば、従業員数50名の製造業の企業に対して、従業員1,000名以上のIT企業での改善成果を紹介しても、スケールや課題感がかけ離れており参考にしづらいでしょう。一方で、同じ業界かつ売上規模や業務内容が近い企業の事例であれば、「自社でも再現できそう」と感じてもらいやすくなります。
「請求処理にかかる時間が1件あたり15分から5分に短縮」「受注後の対応工数が月30時間削減」など、具体的な変化と業種・企業像をセットで提示することで、数字にリアリティが生まれます。成果を数字で伝えるときは、ただ目立つ数値を選ぶのではなく、「誰が」「どんな状況で」成果を出したのかを意識するようにしましょう。
セッション→商談→クロージングへのシナリオ設計が重要
オフラインセミナーと異なり、ウェビナーでは会場で営業がアプローチすることはできません。そのため、開催中から終了後までを一貫した流れとして設計し、参加者を次のステップへ導くためのシナリオ構築が欠かせません。
特に、どのタイミングで情報を取得し、どのようなアクションに接続させるかを事前に決めておくことが重要です。
ウェビナー中の投票機能やチャット質問、終了後のアンケートなどを活用して、自社への関心度や課題感を把握しましょう。例えば「現場のどこに課題を感じているか」といった設問を入れておくことで、営業担当がその回答をもとに個別にフォローを行えます。
信頼関係を築いたうえで、「個別相談会への案内」や「無料トライアルへの申し込み」を自然に提示すれば、次の行動につながりやすくなります。
■まとめ|ウェビナーで成果が出る会社は「市場状況から逆算」している
ウェビナーの成果は、事前の設計段階でほぼ決まるといっても過言ではありません。
とりあえず開催するのではなく、自社の市場状況に応じて「誰に」「どんな価値を」「どのように届けるか」を逆算して企画を組み立てる必要があります。
- 導入企業が少なく認知度も低い場合:課題の存在に気づかせ、必要性を理解させる
- 導入企業が少なく認知度がある場合:自社の優位性を示し、検討対象に加えてもらう
- 導入企業が少なく認知度が高い場合:使用感や効果を伝え、導入後をイメージさせる
- 導入企業が多く認知度も高い場合:実績や再現性を示し、意思決定を後押しする
とはいえ、ウェビナーにはテーマ設定や集客準備、登壇資料の作成、開催後の分析や改善まで、多くの作業が伴います。
「社内だけでは負担が大きい」「継続的に実施する余力がない」といった課題をお持ちであれば、フラグアウトのウェビナーBPOをご検討ください。
企画から運営、改善提案までを一貫して支援し、成果につながるウェビナーをご提案します。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。